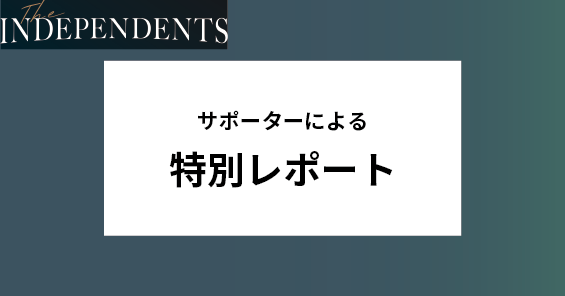公開

國學院大学
教授 秦 信行 氏
野村総合研究所にて17年間証券アナリスト、インベストメントバンキング業務等に従事。
1991年JAFCO に出向、審査部長、海外審査部長を歴任。
1994年國學院大学に移り、現在同大学教授。1999年から約2年間スタンフォード大学客員研究員。
日本ベンチャー学会理事であり、日本ベンチャーキャピタル協会設立にも中心的に尽力。
早稲田大学政経学部卒業。同大学院修士課程修了(経済学修士)
ベンチャーコミュニティを巡って
日本の大企業と中小企業の関係、特に自生的な経済発展が明治時代以前から相当程度見られ、その結果それなりの自営的な事業組織がかなり存在していたところに欧米の近代的な産業が接木された故に近代的な産業の開花が急速に実現したと考えられる日本では、大規模組織を中心にしたそうした近代的な産業・企業と、自生的な発展は見せてはいたものの生産性の低さを引きずっていた中小企業との経済的な格差は大きく、第二次世界大戦中の戦時体制下において、多くの産業で強制的に大規模企業の下に中小企業が下請けとして再編成されることとなり、それが戦後にも引き継がれていったことによって、日本の大企業と中小企業との間の溝は大きくなったと考えられる。
戦後1948年(昭和23年)に中小企業庁が設立され、中小企業政策が検討される中で最初の中小企業基本法が制定されたのが1963年(昭和38年)であった。この基本法で中小企業は二重構造論に基づく考え方によって、大企業との格差は永久に埋まらないとの認識の下に、中小企業は政策的に救済され、保護されるべき存在と位置付けられた。
その後、日本の多くの中小企業を組み込んだ下請システムは日本の国際競争力を支える有力な仕組みとして世界的に評価されたが、中小企業自体の日本での評価は1963年の中小企業基本法の見方から大きく変わることはなかった。
中小企業の位置付けは1990年以降、下請システムの変容、大企業の弱体化、革新的なベンチャーの登場などにより変化し1999年の中小企業基本法の抜本的な改正に繋がっていく。この改正で中小企業の位置付けは、新たな産業創出や就業機会の拡大の担い手というポジティブなものへと変わったが、それまでの長い歴史もあり、大企業と中小企業、更にはベンチャーとの間の溝は依然大きいように思う。
こうした企業規模による評価の違いはどの国でも共通なのだろうか。少なくとも米国を見る限りそうした違いや溝は日本ほど大きくはないように見える。だからこそ米国では活発に大企業が中小ベンチャーを買収し、新しい事業開発に結び付けることが可能になっているのではないか。ちなみに、案件ベースで見た米国VCの資金回収方法において最近では90%以上がIPOではなくM&Aになっている(NVCA“Yearbook2017”参照)。
既にこのコラムのどこかで述べたように、米国ベンチャーはかなり前から、実はアップルやグーグルのようにそれ自身でIPOして大きくなっていくベンチャーが目立つ一方で、基礎技術を大企業などからライセンスアウトしてもらい、起業家のアイデアを基に事業化にトライし、軌道に乗ったところでM&Aで大企業傘下に入り、大企業の資金で事業部ないしは子会社として成長していくベンチャーが数的には多いのではなかろうか。
こうした状況を日本でも創り出していくことが求められる。幸い、最近大企業側が新規事業開発を喫緊の課題として位置付け、中小ベンチャーに接近し始めており、両者間の溝は埋まりつつあるように見える。こうした動きを何とか定着させたい。
※「THE INDEPENDENTS」2018年5月号 掲載