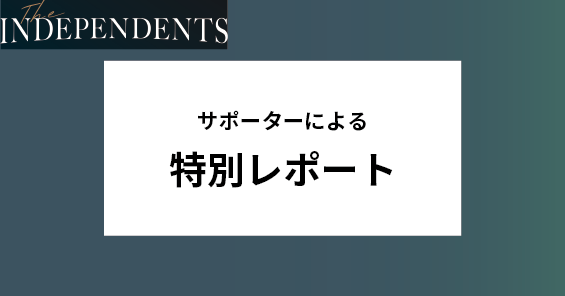公開

弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士 溝田 宗司 氏
2002年同志社大学工学部電子工学科卒業後、株式会社日立製作所に入社。特許業務等に従事。2003年弁理士試験合格(2003年12月登録)。2005年特許コンサルタントとして活動。2005年04月大阪大学高等司法研究科入学。2008年03月大阪大学高等司法研究科修了。2009年09月司法試験合格/11月司法研修所入所(新63期)。2010年12月
弁護士登録。2011年01月内田・鮫島法律事務所入所。
【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】 http://www.uslf.jp/

1.前回の概要
前回、ノウハウだけで技術を保護する方法として、不正競争防止法上の救済手段について述べました。今回は、秘密保持契約による法的救済手段について見ていきたいと思います。
2.秘密保持契約上の法的救済手段
秘密保持契約は、共同でビジネスを開始する際に必ずと言っていいほど締結されるものです。それだけに甘く見がちで、ひな型で済ませている方も多いのではないでしょうか。
大抵の秘密保持契約では、「秘密情報」につき、(1)開示・漏えいの禁止、(2)目的外利用の禁止が規定されています。この両者を混同されている方も多いですが、特に重要となるのが(2)の「目的外利用の禁止」です。「目的外利用の禁止」というからには、「目的」をある程度具体的に定めなければなりません。また、「秘密情報」の定義も重要です。「一切の営業上、技術上の情報」等と規定されている契約書も散見されますが、自社が守りたいと思う情報については具体的に記載した方が、後々疑義が生じません。このあたりは、ひな型では対応できませんので、専門家のチェックを受ける必要があります。
また、海外との取引の場合には、準拠法や裁判管轄といった問題も生じますが、それは別の機会に触れたいと思います。
こういった規定について適切に定めている場合に、情報受領者が開示者の秘密情報を目的外に利用した場合(例えば、共同ビジネス以外のビジネスに流用した場合が典型例です。)、契約違反についても責任追及が可能となります。もちろん、当該秘密情報が不正競争防止法上の「営業秘密」に該当すれば、同法上の責任追及も併せて可能となります。
ここで、「ウチは、秘密保持契約をしっかり作っているから大丈夫だ。特許なんていらない。」と思われる方もいるかもしれません。確かに、秘密保持契約を締結することで契約上、開示・漏えいや目的外使用を禁止することができます。しかし、別の問題があるのです。それは、「目的外利用の立証の困難性」です。
秘密保持契約では目的外利用禁止規定を置くのが通常ですから、秘密情報(ノウハウ)の受領者は、この目的に反して秘密情報を利用した場合、法律上、債務不履行にあたり、損害賠償義務を負うことになります。
ただ、この場合、債務不履行についての立証責任は秘密情報の開示者にありますから、開示者の方で目的外に利用されたことを証明しなければなりません。
これは容易なことではありません。その理由は、(1)目的外利用は、情報受領者の支配領域内(敷地、工場など)でなされるのが通常であるがゆえに、目的外に利用されたかどうかを外形的に判断することが難しい、(2)受領者が大企業などの場合、当該情報を独自に開発したことを主張立証されてしまうと、仮にそれが虚偽であったとしても、反論するのが難しい。
結局は、目的外に利用したのか独自に開発したのか、すべて受領者の支配領域の出来事なので、立証するのが困難ということになります。
もっとも、対策はあります。例えば、秘密情報の開示時期と目的外利用の時期(秘密情報を用いた製品の販売日などから逆算することで求められる)がどのくらい近いか、秘密情報を受領した部門と秘密情報を目的外利用した部門(秘密情報を用いた製品の製造・販売部門など)の関係、秘密保持契約締結後の開示者と受領者間の取引の関係などから、秘密情報を目的外利用したことを立証することは可能ではあります。
しかし、依然としてハードルが高く、秘密保持契約を締結しておけば万全とは到底いえません。
【第4回】ノウハウを保護するには
【第3回】ノウハウとしての技術保護
【第2回】ステップ1.― 創生⇒保護⇒活用のサイクル ―
【第1回】中小企業における特許の必要性
【講演レポート】小説「下町ロケット」より 中小企業の知財戦略(鮫島正洋)
※「THE INDEPENDENTS」2013年7月号 - p15より