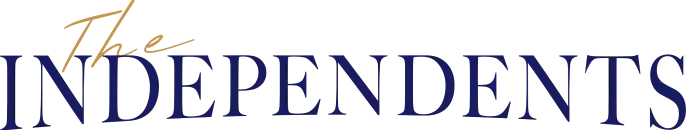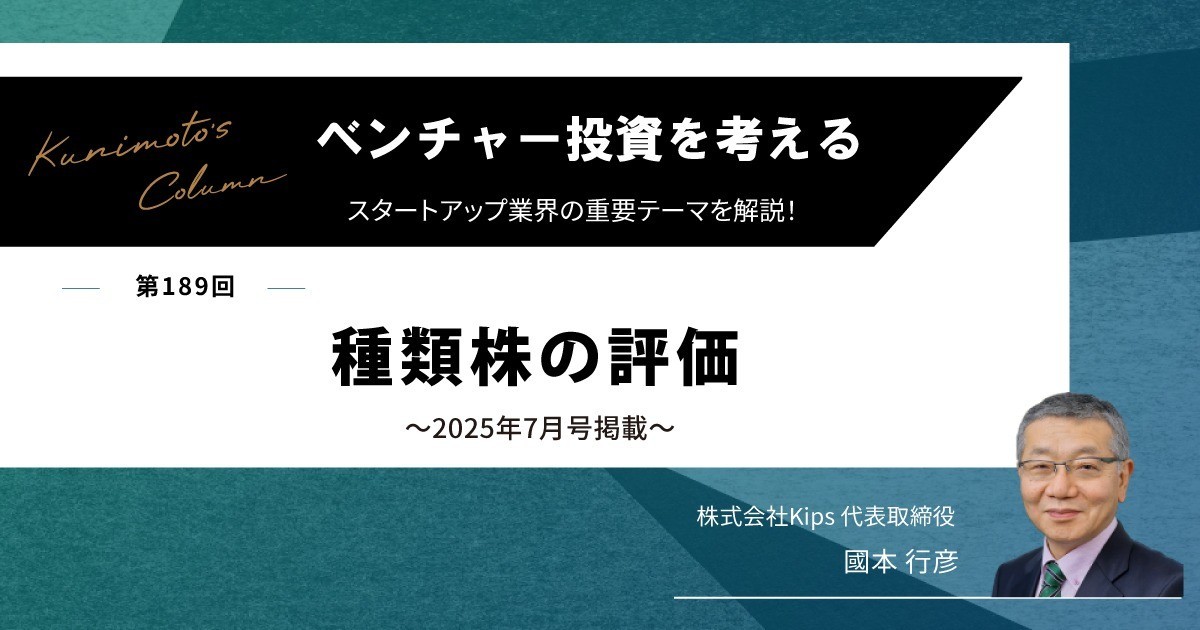|
【國本 行彦】 1960年8月21日生。 東京都立志村高校卒業。 1984年早稲田大学法学部卒業後、日本合同ファイナンス(現・JAFCO)入社。 2006年1月5日(株)インディペンデンツ(現(株)Kips)設立、代表取締役就任。 2015年11月9日 特定非営利活動法人インデペンデンツクラブ 代表理事就任(現副代表理事) 2020年6月 (株)ラクス社外取締役就任 |
種類株の評価
米国のUSスチールが拒否権付きの「黄金株(ゴールデンシェア)」を無償で発行します。これは経済的な見返りを目的とせず、経営方針の変更や敵対的買収に対して特定の株主が拒否権を行使できる、いわばガバナンス上の防衛手段として機能する種類株式です。日本でも、INPEXがこれに類似した黄金株を発行し、普通株を上場しています。
日本のベンチャー企業においても、種類株式の活用は広がっています。とりわけ優先株は、清算優先権や転換権、希薄化防止条項などの経済的な権利が付されたもので、普通株式に対してプレミアム(加算価値)が発行条件に基づいて加味されますが、未上場企業のA種優先株は20~30%前後を目安とすることが、税務的にも説明しやすい実務的な対応とされています。
一方、創業者が経営支配権を維持する目的で用いられるのが、黄金株や多議決権株です。黄金株は特定の重要議案に対して拒否権を持つ株式であり、通常は経済的価値を伴わず、1株のみ発行されることが多いです。多議決権株は、1株に複数の議決権を与える種類株で、例えば1株に10議決権を設定することで、持株比率が低くても経営への影響力を維持できます。これらはいずれも、普通株式とは異なる権利内容を持つため、定款での明確な設計と開示が必要です。
こうした種類株は経営の安定化には寄与しますが、税務や上場審査の観点では慎重な設計が求められます。たとえば、配当受領権等がなく経済的価値を持たないと設計した種類株でも、議決権に大きな偏りがあれば「支配権プレミアム」があるとして贈与税の課税対象になる可能性があります。
また、上場審査においては、1株1議決の原則が重視されるため、上場時点で普通株に転換され、消却されていない種類株が残ることは原則として認められていません。実際に、創業者が多議決権株を持つ種類株式を保有したまま上場した事例としてはCYBERDYNEがありますが、これは例外的に許容されたケースであり、上場準備企業が同様のスキームを採用する場合には、主幹事証券会社や東証との十分な事前協議が必要です。
税務上のリスクも見逃せません。投資家が優先株に高額で出資した直後に創業者が親族に普通株を低価格で譲渡した事案では、普通株の評価に合理性がなく「みなし贈与」とされ課税された判例(東京地裁平成23年(行ウ)第100号)があります。また、ストックオプションの発行価格が著しく低かったことで、役員報酬として課税されたケースもあります。
※本記事の一部は、生成AI(ChatGPT)を活用して作成・編集されています。
※多議決権は、普通株1株=1単元に対して、種類株1株に例えば10単元(=議決権10倍)を与える同時に無配当等など経済的メリットを抑える設計にします。
※「THE INDEPENDENTS」2025年7月号 - P.15 より