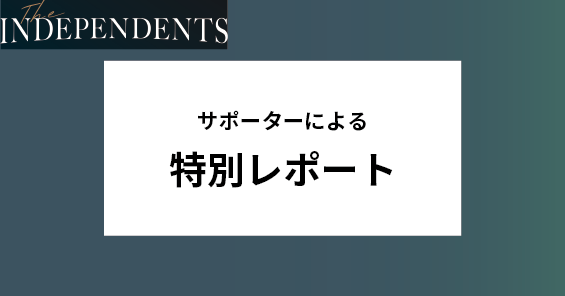公開

早稲田大学大学院商学研究科
教授 松田 修一さん
1943年 山口県大島郡出身
1966年 公認会計士試験第二次試験合格(1971年公認会計士)
1967年 早稲田大学商学部卒業
1972年 早稲田大学大学院商学研究科博士課程修了
1973年 監査法人サンワ事務所(現トーマツ)入所・パートナー
ベンチャー企業の倒産回避・成長支援、ベンチャーキャピタルの成長支援に従事
1985年 「独立第三者による経営監査の研究」で商学博士授与(早稲田大学)
1986年 早稲田大学システム科学研究所(アジア太平洋研究センター)助教授
1990年 ボストン大学客員教授
1991年 早稲田大学システム科学研究所(アジア太平洋研究センター)教授
1993年 早稲田大学アントレプレヌール研究会を組織、代表理事(現在)
1997年 日本ベンチャー学会副会長
1998年 エンジェル・ファンドとしてウエルインベストメント(株)設立、取締役(現在)
早稲田大学大学院(MBA:国際経営学専攻)教授
2002年 早稲田大学アジア太平洋研究センター所長 アジア太平洋研究科委員長
2003年 早稲田大学大学院アジア太平洋研究科 国際経営学専攻(専門職大学院:MOT担当)教授
2004年 日本ベンチャー学会会長(現在、理事・制度委員会委員長)
2007年 早稲田大学大学院商学研究科(ビジネス専攻)教授(現在)
I.日本の置かれている現状
成熟国家となった日本では、高度成長期といわれる1970年頃の実質GDP成長率10%に対し、2%の成長に留まっています。一方、今まさに高度成長国家と言われる中国やインドは、1970年前後の日本のそれと同じ速さで成長しています。そして20年後には、2011年現在の日本と同じ状況に、中国やインドがなると考えられています。先立って成熟国家、すなわち課題先進国になった日本は、今後国としてどう歩んでいくべきなのでしょうか。
世界一人当たりGDPと起業活動率マップ(Global Entrepreneur Monitor調査)を見ると、日本は1人あたりGDPの割に、起業活動率は低く位置しています。これは、最近経済破綻が危惧されているイタリア等と同じレベルです。一方、アメリカや韓国は高い起業活動率を誇っています。それぞれ移民率の高さや北朝鮮との位置関係が、起業活動率に影響しているのでしょう。
国比較の国民税負担率を見ると、日本は法人税が7.1%と突出して高いことが見て取れます。税率で見ても日本は40%であり、EU30%、韓国25%、シンガポール20%とかなり高い水準です。消費税を見ても、アメリカは12%と高いように見えますが、徴収額比率は日本の方が高いのです。アメリカでは必要最低限の消費には税金をかけていないからです。日本では社会政策と経済政策が混同してしまっています。ベンチャーを支援するような経済政策と、セーフティネットのような社会政策は、本来別問題として議論しなければなりません。
II.日本経済のスピード感と産業構造
30年で日本が米国に、15年で中国が日本に追いつき追い越そうとしていることが歴史から見て取れます。1960年代、当時日本も米国の生産技術をいかにキャッチアップするかに多くの力を注いできました。70年前後には、富士通や日立がIBMに訴訟されたほどです。今、それを中国が日本に対して行っている状況です。インターネットが普及した今、そのスピードとコストは以前とは格段に違います。
世界のイノベーションエンジン25社の産業構造を見ても、日米の違いは明らかです。アメリカでは、1970年代以降に設立された企業9社が、ビジネスウィークが発表ランキングにノミネートされています。80年代に日本企業によって製造業が駆逐された後、新しい産業構造を作ってきたからです。一方、日本では企業も政策もものづくりに固執し、ITなど時代の流れに乗り遅れてしまっています。
オリンピックが中国の勢いと日本の課題を語っています。08年に北京五輪を開催した中国には、東京五輪によって引き起こされたいざなぎ景気時の日本と同じ勢いがあります。それほどのスピード感が、今の中国にはあるということを、日本は認識するべきです。
中国は過去30年と今後30年で、大きく変貌していくと思われます。外資誘致・積極輸入・インフラ整備を通じて、技術立国を目指しています。「三流企業がものを作り、二流企業が技術を開発し、一流企業がルールを決める」とは中国の起業家の言葉です。彼らは巨大なマーケットを背景に、世界のデファクトスタンダードを作ろうとしています。
2050年世界のGDPに占めるアジアの割合は54%になるとゴールドマン・サックスが発表しました。世界全体のトレンドは人口と若さであり、すなわち活力なのです。ベンチャーを経営するなら、若い人の力をどう発揮させるかを考えるべきです。経営者自身も、自分のビジネスは何歳であれば世界と戦えるのか、検討する必要があります。
III.ベンチャーにイノベーション(第三の創業)が期待できるか
日本の基盤を創った会社は、その多くが戦争を挟んだ前後30年に設立されています。共通して言えることは、非財閥系・創業者の遺伝子継承・消費者直結・変化対応力があったことです。
世界の主要新興市場のIPO数の推移を見ると、ロンドンAIMが2071社と圧倒的です。イギリスは証券市場の活性化によって、経済発展を目指してきました。一方、日本は744社。今の時代に合った取引所運営が求められています。世界は待ってくれません。
日本のIPO数の業種別推移を見ると、情報・サービスが最も多くなっています。しかし、新聞株式欄等では製造業に関する記事が依然多いのも事実です。この業種において世界に冠たる企業が出てくる事が求められています。
気力・知力・体力一体の自律社会を、今こそ目指すべきです。大企業が続々と海外に拠点を移している中、ようやく経済産業省も文科省もベンチャー育成に本腰を入れて取り組もうとし始めています。これから迎える高齢化社会を、官に依存せずどれだけ乗り越えられるか、ベンチャーの力が試される時がきています。
経営資源を活かす総合的事業構想人材を育てる必要があります。バリューチェーンの統合や技術の深化と拡張を、クローズとオープンを切り分けて加速させるなど、大きく発想できることが求められています。中途半端が何より問題です。大学発ベンチャーも、試作品の山で潰れてしまっているケースが大半なのです。
IV.ベンチャーのエコシステムを
イノベーション・エコシステムに関する答申案を今年5月にベンチャー学会に提出しました。特に大学発ベンチャーをどう育てるかについて、弁理士会の前々会長が技術からマーケット創出まで本気になって取り組んでいます。コア技術やリスク資金を入り口に、IPOやM&Aなどの出口まで、どうやってベンチャーを支援していくか、どうやって資金や人材を循環させるか、生態系の整備が急務です。
米国のベンチャーキャピタルのExitにおいて、IPOとM&Aのキャピタルゲインに同額性が見て取れます。そのために、最も重要なことは「システマティックなプロ経営チームを作れるか」ということです。米国ではマイクロソフトやDellなどの稀なケースを除き、成功モデルはほぼ30代半ばの経営チームです。20代後半にMBAを取得し、200人ほどの成長企業にマネージャーとして参画し、開発・販売・管理のプロフェッショナルなど事業パートナーを集めてから起業しています。
日本の大学研究知が活かせるかどうかも重要です。大学発ベンチャーにおいて、文科省に対する研究開発予算を申請する書類をキャピタリストが作成してよいなど、量から質への転換が図られ始めています。
中国の大学発ベンチャーには、凄まじい支援システムがあります。大学で建設部門やインキュベーション機能、TLO(技術移転機関)、ベンチャーキャピタルを持っているのが普通です。清華大学では、清華同方股分有限公司というビルの遠隔集中管理技術をコアに売上1974億円(08年)もある企業を生み出しています。中国のトップ10の大学は皆こういった仕組みを持っており、アメリカに引けをとらないレベルです。
V.ボーン・グローバルベンチャーを
ボーン・グローバルベンチャーが日本でも育ちつつあります。今こそ、日本を基点に起業する意味を見つめなおすべきです。顧客の満足度基準が著しく高いこの国において、商品・サービスのブラッシュアップを行うパイロット国家として活用することは有効です。そして、契約関係や知財管理を誤らず、世界に向けて収益モデルと資金モデルを確立させることが重要です。
日本の「ほら吹き」3人男とは、日本電産永守氏の言葉であり、ソフトバンク孫正義氏、ファーストリテイリング柳井正氏、楽天三木谷浩史氏を指します。3人に共通するのは、現状と目標値のギャップがものすごくあることです。この言葉の真意は、ほらを吹くほど大きな目標を立てなければ、そこに至るまでの努力はできないということです。
米国建国時代のアントレプレナー宣言を、最後に皆さんに贈りたいと思います。「私は平凡な人間にはなりたくない。自らの権利として限りなく非凡でありたい。私が求めるものは、保証ではなくチャンスなのだ。(以下略)」。日本は、豊かさは手に入れましたが、こういった精神性はまだまだこれからです。本日はご静聴ありがとうございました。
*2011.11.8 静岡インデペンデンツクラブ
【特別寄稿】事業計画発表会、次なる100回目を目指して(松田修一)
※全文は「THE INDEPENDENTS」2012年1月号 - p28-29にてご覧いただけます