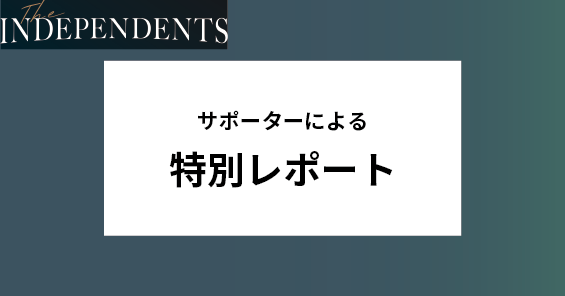公開

弁護士法人 内田・鮫島法律事務所
弁護士 溝田 宗司 氏
2002年同志社大学工学部電子工学科卒業後、日立製作所にて特許業務等に従事
2003年弁理士試験合格(同年12月登録)
2005年特許コンサルタントとして活動
2005年04月大阪大学高等司法研究科入学、2008年03月修了
2009年09月司法試験合格/11月司法研修所入所(新63期)
2010年12月弁護士登録
2011年01月内田・鮫島法律事務所入所
【弁護士法人 内田・鮫島法律事務所】
http://www.uslf.jp/

■ 前回まで
前回までにお伝えしたとおり、「強い特許=必須性×検出性×有効性」となります。
今回からは、上の公式の内、「有効性」を確保するためにどのようにすればよいのかをお伝えします。
■ 有効性を確保するための手法
有効性を確保するためには、よくいわれるように、出願前に公知例調査を実施し、調査で発見された公知例を意識した内容の権利を取得するということ、発明発掘を適切に行い明細書(注:発明の内容について解説している書類のこと)を多数記載しておくということに尽きます。詳しく説明します。
特許の出願時には、発明の内容を特許請求の範囲(注:権利の内容について説明している書類のこと。「クレーム」ということもあります。)に正確に記載することが試みられると思います。しかし、正確であることよりも必須性、そして何よりも公知技術を意識する必要があります。
特許要件(発明が特許されるための要件)は、大きく分けて新規性・進歩性・産業上利用可能性の3つがあります。ここで重要なのは新規性と進歩性です。平たくいえば、発明は、公知技術と対比して新規であり、かつ進歩していれば特許されるということです。発明が特許になるか否かは、発明の内容が世紀の大発明でなければダメだとかそういうことは関係がありません(そういう意味では学術論文などとは異なります)。つまり、特許とは相対的なものなのです。そのことを認識した上で、発明者の考える発明のポイントを意識して公知例調査を実施し、その結果を踏まえて、その発明が公知技術の何を課題として捉えているのか、その課題をどう解決したのかという形に再構成し直します。そして、再構成し直したものを明細書に記載します。
ここで重要なのは、再構成した公知技術や課題を、明示的かつ具体的に記載することです。そうすることで、後日、訴訟になった場合に一見似た公知技術を突き付けられても、突っぱねることが可能となります。
この点、課題を抽象的にしか書いていない明細書も散見されます。できるだけ広い権利を取りたいということだと思うのですが、広い権利を取っても使えなければ意味がありません。つまり、課題を抽象的に記載すると発明(特許権)が抽象的になってしまい、その結果、公知技術との差別化が図れないということがあります。
訴訟では、裁判官は、原則として、明細書に明示的に記載されている公知技術や課題を主軸として発明を把握します。もちろん、明細書に明示的に記載されていない公知技術や課題から発明を把握することがないわけではないのですが、発明から何年もたって発明を把握しなければならない裁判官の立場を考えれば、明示的に記載されている事項とそうでない事項のどちらを重視するのかは明らかでしょう。また、公知技術や課題を具体的に記載しておくことで、後日の訴訟の場面で説得的な主張が可能となり、裁判官も発明のポイントを把握しやすいということになります。
※「THE INDEPENDENTS」2014年11月号 - p15より
【中小企業の特許戦略第18回】強い特許(1)
【中小企業の特許戦略第18回】強い特許(2)